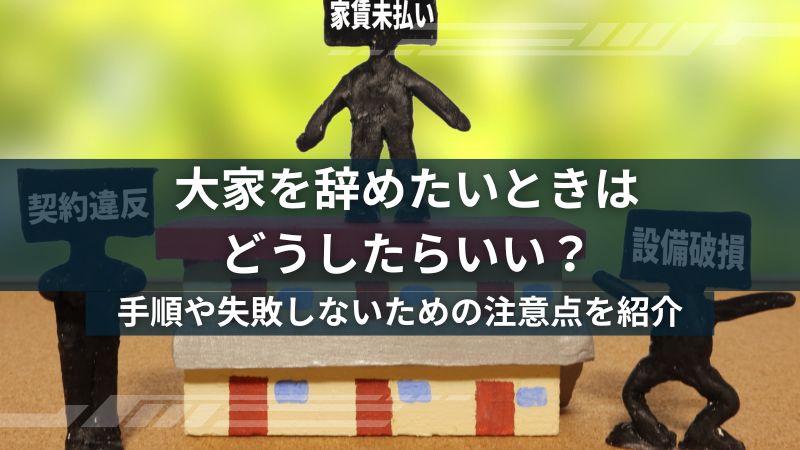空室率の増加や老朽化による修繕費の負担、管理の手間などで、家業を辞めたいと考える方は少なくありません。
しかし、いざ大家を辞めようと思っても、どのような手順を踏めばよいか分からず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
大家業を辞める適切なタイミングや売却や廃業のリスク、成功するためのポイントを詳しく解説します。
大家業の撤退を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
大家を辞めるのに最適なタイミングとは?
不動産経営は長期的な視点が求められますが、状況によっては辞めることが最善の選択である場合もあります。
たとえば、空室が増えて経営が厳しくなったり、建物の老朽化が進んで修繕費が負担になったりするケースでは、早めに撤退を考えるのも一つの手です。
大家業を辞めるのに適したタイミングを6つご紹介しますので、ご自身の状況と照らし合わせ、今後の方針を決める際の参考にしてください。
空室率が高く改善が難しいとき
運営する物件の空室率が高く、改善が難しいと感じる場合は、大家業を辞めるタイミングとして適しています。
空室が続くと家賃収入が減り、維持費や固定資産税の負担が重くなります。
特に、築年数が古い物件や立地が悪い場合、入居者を集めるためにリフォームや賃料の値下げが必要になり、経営が厳しくなるケースもあるでしょう。
空室率をなかなか下げられないときは、売却や廃業を検討するのが得策です。
建物が老朽化してきたとき
建物の老朽化が進むと、修繕費や維持管理費が増加し、大家業の負担が大きくなります。
特に、築30年以上のアパートは外壁や屋根、防水設備の劣化が進み、大規模修繕が必要になるケースが大半です。
修繕を怠ると、入居者や近隣に住む方々の安全性に影響を及ぼし、空室率の増加や家賃の下落につながる可能性があります。
さらに、耐震基準の問題や給排水設備の老朽化も考慮が必要です。修繕コストが家賃収入を圧迫する場合は、売却や廃業を検討してみてください。
ローンをすべて払い終えたとき
ローンを完済したタイミングは、大家業を辞める絶好の機会の一つです。
ローンが残っている状態で不動産を売却し、売却価格がローン残高を下回る場合、自己資金を補填しなければならないリスクがあります。
しかし、ローンを完済していれば売却時の手取り額が増え、自由に資産を処分できます。
さらに、ローン返済のプレッシャーがなくなることで、収支を見直し、今後の選択肢を広げることが可能です。大家業を続けるか辞めるかを再検討し、売却や資産整理を進めるのに適したタイミングと言えます。
予期せず賃貸物件を相続したとき
予期せず賃貸物件を相続した場合、大家業を続けるか辞めるかを慎重に検討する必要があります。
相続した物件が老朽化していたり、空室が多かったりすると、維持費や管理の負担が大きくなります。さらに、固定資産税や修繕費などのコストも考慮しなければなりません。
また、不動産経営の知識がない状態で大家業を続けることもリスクが伴います。
もしも賃貸経営の負担が大きいと感じる場合は、売却や管理会社への委託を検討しましょう。
家賃収入よりも維持費がかさむとき
家賃収入よりも維持費が増え続けると、大家業の継続は厳しくなります。
固定資産税や管理費、修繕費などのコストが増加し、家賃収入だけではカバーできなくなると、経営はさらに圧迫されます。
築年数が古い物件や立地条件が悪い場合、家賃を下げても入居者が集まりにくく、負担が増す一方でしょう。
このような状況では、早めに売却や廃業を検討し、損失を最小限に抑えることが重要です。
家族の事情やライフスタイルの変化で管理が困難になったとき
家族の事情やライフスタイルの変化によって、賃貸物件の管理が難しくなった際も、大家業を辞めるタイミングの一つです。
例えば、転勤や介護、健康上の問題などで物件の維持管理に時間や労力を割けなくなるケースがあります。また、高齢になるにつれて、修繕対応や入居者トラブルの管理が負担に感じる方もいます。
このような場合、管理会社に委託する選択肢もありますが、収益が見合わない場合は売却や廃業を検討するのがおすすめです。家族とも相談し、今後のライフプランに合わせた最適な判断をしましょう。
大家を辞める5つの方法
大家業を辞めるには、物件の売却や別の用途に転用する方法、ローン返済が厳しくなった際の任意売却など、いくつかの選択肢があります。
大家業を辞めるための5つの具体的な方法について詳しく解説します。
オーナーチェンジで物件を売却する
大家業を辞める方法の一つとして、オーナーチェンジによる物件売却があります。
オーナーチェンジとは、現在の入居者が住んだままの状態で物件を売却し、新しいオーナーへ所有権を引き継ぐ方法です。入居者を退去させる必要がないので、立ち退き料を支払うことなく物件を手放せることが大きなメリットです。
また、賃貸契約が継続されるため、買い手にとって安定した収益が見込める投資物件であれば、スムーズな売却が期待できます。特に、空室率が低く家賃収入も安定している場合、売却価格も高くなる可能性があります。
一方、オーナーチェンジのデメリットとして、市場価格よりも売却価格が下がる可能性がある点には注意が必要です。
物件を解体して更地の状態で売却する
老朽化が進んだアパートや空室が多くなった物件は、解体して更地の状態で売却するのも一つの方法です。
建物付きの物件として売却する場合、購入希望者が限られることがありますが、更地にすることで活用方法の自由度が高まり、売却しやすくなるメリットがあります。
また、築年数が古い物件は建物の評価が低く、売却価格が伸びにくいことが多いですが、更地にすることで土地の価値を重視した価格設定が可能になります。
特に、立地が良い場合や新たに住宅や商業施設として活用できる場合は、更地にすることで買い手がつきやすくなります。
ただし、解体費用がかかる点や、更地にすることで固定資産税の優遇措置がなくなる可能性がある点には注意が必要です。解体費用と売却価格のバランスを考えながら、最適な方法を選びましょう。
賃貸物件以外の建物に建て替える
大家業を辞めたいものの、土地を手放さずに有効活用したい場合は、賃貸物件以外の建物に建て替える方法もあります。
たとえば、自宅として活用する、駐車場や貸倉庫、テナントビルなどに転用することで、管理の手間を減らしつつ収益を得ることも可能です。
特に、駐車場経営は初期投資が比較的少なく、管理の手間も賃貸物件より少ないため、負担を軽減しながら土地を活用できます。また、立地によってはコインランドリーやトランクルームなど、需要の高いビジネスに転用することで、安定した収益を見込めるかもしれません。
ただし、建て替えには解体費用や建設費用がかかるため、将来的な収益とコストのバランスをしっかり検討することが重要です。専門家と相談しながら、最適な活用方法を見極めましょう。
相続・贈与で権利を引き継いでもらう
大家業を辞める方法として、家族や親族に物件を相続・贈与して引き継いでもらうことも一つの選択肢です。
特に、すでに不動産経営を行っている家族がいる場合や、後継者として物件を活用したいと考えている人がいる場合には、有効な手段となります。
相続の場合、所有者が亡くなった後に法定相続人が物件を受け継ぐことになりますが、生前に遺言書を作成しておくと、スムーズに権利を移行できるため事前の準備が大切です。
贈与の場合は、生前に物件を譲ることで、計画的に資産を移転できます。ただし、贈与税が発生する可能性があるため、税金対策として相続時精算課税制度や暦年贈与の活用を検討しましょう。
相続・贈与による引き継ぎは、相続人全員で十分に話し合いを行い、将来的な経営の意思を確認することが重要です。また、税理士や不動産の専門家に相談し、最適な方法を選択することをおすすめします。
ローン返済が困難になったときは任意売却・競売も検討する
大家業を続ける中で、ローンの返済が厳しくなった場合は、任意売却や競売を検討することも選択肢の一つです。
任意売却とは、金融機関と交渉し、ローン残債がある状態でも物件を売却する方法です。通常の売却と異なり、ローン残高が売却価格を下回っても、金融機関の同意を得られれば売却が可能になります。
任意売却のメリットは、市場価格に近い金額で売却できる可能性が高いことや、競売と比べて所有者の意向をある程度反映できることです。
一方競売は、ローンの返済が滞り、金融機関が裁判所を通じて強制的に物件を売却する手続きです。競売は市場価格よりも大幅に低い価格で落札されることが多く、売却後もローンの残債が残る可能性があるため、できる限り回避したい手段です。
競売を避けるためには、できるだけ早く金融機関と相談し、任意売却の交渉を進めることが重要です。
大家を辞めるときの流れ
賃貸物件を売却して大家業を辞める際には、手続きを進めるために適切な流れを把握しておくことが重要です。
以下に、賃貸物件を売却する際の一般的な流れを紹介します。
- 物件の売却方針を決める
- 不動産会社に査定を依頼する
- 売却活動を開始する
- 買主と売買契約を締結する
- 決済・物件の引き渡し
- 売却した翌年に確定申告を行う
なお、査定の際には、築年数や立地、家賃収入の状況、修繕履歴などが考慮されます。
不動産投資家向けに売る場合は、年間の収益性が重視されるため、収支シミュレーションを用意しておくのがおすすめです。
また、売買契約の際には、売却物件の現状や修繕履歴、家賃収入の情報を正確に伝えましょう。オーナーチェンジの場合は、既存の賃貸借契約や管理会社の引き継ぎについても話し合う必要があります。
大家を辞めるときのリスクや注意点
大家業を辞めることを決断した際には、単に物件を売却すれば終わりではなく、さまざまな手続きや税務処理が必要になります。
ここでは、大家業を辞める際に注意すべきポイントや、リスクを回避するための対策について詳しく解説します。
立ち退きでトラブルが発生する恐れがある
賃貸物件の売却で入居者に退去してもらう場合、立ち退きによるトラブルが発生する可能性があります。
特に、長期間住んでいる入居者や、相場より低い家賃で契約しているケースでは、立ち退き交渉が難航しやすくなります。入居者側にも住み続ける権利があるため、大家の都合だけで退去を求めることはできません。
退去させるには正当事由が必要
日本の法律では、貸主の事情で入居者を退去させる場合には「正当事由」が必要とされています。正当事由として認められるのは、建物の老朽化で住み続けることが困難な場合や、大規模な建て替え・再開発が必要な場合などです。
また、大家自身やその家族が居住する必要があるときも、正当事由として認められることがあります。
強制的に退去させることは難しい
立ち退きを求める際は、入居者の生活状況や家賃の支払状況なども考慮されるため、一方的な通告では退去を強制できません。立ち退き交渉の際は、弁護士や不動産専門家に相談するのが安全です。
入居者が立ち退きに応じない場合、交渉が長期化すると、最終的には裁判所の判断を仰ぐことになります。
そのため、強引に退去を求めるのではなく、丁寧に説明し、入居者の理解を得ながら進めるようにしてください。
期限までに廃業届を提出する必要がある
大家業を辞める際は、廃業届を適切な期限内に提出する必要があります。賃貸経営を個人事業として行っている場合、廃業する際には個人事業の開業・廃業等届出書を税務署に提出しなければなりません。
廃業届の提出期限は、大家業を辞めた日から1カ月以内が原則です。たとえば、物件を売却し、家賃収入が途絶えた時点で廃業となるため、その日から1カ月以内に税務署に届け出る必要があります。
また、事業所得として青色申告をしていた場合は、「青色申告の取りやめ届出書」の提出が必要になります。さらに、消費税の課税事業者である場合は「消費税の事業廃止届出書」も税務署に提出しなくてはいけません。
大規模な大家業を営んでいた場合、税務手続きが複雑になる可能性があるため、税理士に相談しながら手続きを進めると安心です。
青色申告を利用できなくなる
青色申告は、一定の条件を満たす個人事業主が利用できる制度で、最大65万円の特別控除や、赤字を3年間繰り越せるなどの税制上のメリットがあります。
しかし、大家業を廃業すると事業所得ではなくなり、青色申告の適用対象から外れます。
特に、複式簿記による65万円控除や、赤字の繰越控除ができなくなる点は、税金面での負担増につながる可能性があるでしょう。さらに、青色申告で認められていた家族への給与も、廃業後は経費として計上できなくなるため、所得税に影響を及ぼす場合があります。
廃業後、大家業を継続せずに不動産を売却する場合は、売却益が譲渡所得として課税されます。
また、売却せずに賃貸を続ける場合でも、事業的規模(5棟10室基準)を満たしていない場合は「不動産所得」として課税の対象となり、税制上の優遇措置が適用されない可能性があります。

- 高値売却かつ早期売却したい方におすすめの不動産会社 No.1 ※
- 知人に紹介したい不動産売却会社 No.1 ※
- 相続の相談をお願いしたい不動産売却会社 No.1 ※
トップファーストでは、全国の一棟アパートや一棟マンションといった収益物件をはじめ、様々な不動産を取り扱っております。
相続や資産整理といった不動産に関するご相談も、実績豊富な当社にお気軽にお問い合わせください。高い専門知識を持ったスタッフが問題解決をお手伝いいたします。
2023年2023年5月期_ブランドのイメージ調査(調査1~3)
調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
調査期間:2023年3月14日~2023年5月31日
n数:129(※調査1)、124(※調査2)、136(※調査3)/調査方法:Webアンケート
調査対象者:https://jmro.co.jp/r01446/
備考:本調査は個人のブランドに対するイメージを元にアンケートを実施し集計しております。/本ブランドの利用有無は聴取しておりません。/効果効能等や優位性を保証するものではございません。/競合2位との差は5%以上。